G-ベクタリング コントロール 共同開発者に聞く Vol.02
クルマの“当たり前の性能” を変える、新技術の意義。
製品化によって明らかになった、GVCの真のポテンシャル。


山門教授:
完成したGVCで衝撃的だったのが、直進にも効果があったことです。私たちは、Gが強く発生するコーナーでのみ実証試験を行っていたので、それは知る由もありませんでした。
最初は信じられなかったのですが、乗ってみると確かに違う。驚くのと同時に、この理論の延長線上に、こんな効果まで発見した探究心に、お見事というしかないですね。
山門教授:
完成したGVCで衝撃的だったのが、直進にも効果があったことです。私たちは、Gが強く発生するコーナーでのみ実証試験を行っていたので、それは知る由もありませんでした。
最初は信じられなかったのですが、乗ってみると確かに違う。驚くのと同時に、この理論の延長線上に、こんな効果まで発見した探究心に、お見事というしかないですね。
安部教授:
私のGVCの印象は、小さなGに対しても敏感にトルク制御を行うため、クルマが非常に安定していることですね。その制御は、ドライバーでは反応できないほどの微小なGにまでおよび、しかもその効果はドライバーにも伝わってくる。想像以上に人間の感覚に訴える技術だと感じました。
今後は単なる車両運動の研究を超えて、ドライバーの動きや操作の間合い、同乗者の姿勢といった、より人間に近い部分を検証していく予定です。完成したGVCが、車両運動力学の研究レベルをひとつ押し上げたという感じですね。
なぜ今までなかったのか。そう思わずにはいられない技術。


安部教授:
GVCが行う制御は、単なる“機械的な制御”ではありません。上手にクルマを動かせる状況だけつくって、あとはドライバーに任せる。曲げるのをやめたら、それ以上は曲がらない。あくまで動かすのは人間。
余計なおせっかいをして運転する楽しさを奪う技術ではありません。そういう意味でGVCは、“人間を中心とした初の車両運動制御技術”といえるかもしれません。
安部教授:
GVCが行う制御は、単なる“機械的な制御”ではありません。上手にクルマを動かせる状況だけつくって、あとはドライバーに任せる。曲げるのをやめたら、それ以上は曲がらない。あくまで動かすのは人間。
余計なおせっかいをして運転する楽しさを奪う技術ではありません。そういう意味でGVCは、“人間を中心とした初の車両運動制御技術”といえるかもしれません。
山門教授:
極端なことをいえば、この技術は、クルマが発明された時に備わっていてもいいぐらいのものだったのではと思います。例えるなら、ハンドルとタイヤをつなぐシャフトと同じような機能をもつ“部品”といえるのではないか。その証拠に、マツダさんはこの技術をすべてのSKYACTIVエンジン・シャシー搭載モデルに採用していくという。
つまり、今後はマツダさんのクルマに欠かせない部品になるということです。そしてこれは、安部先生もおっしゃるように“おせっかいな制御による違和感”を生むものでもない。最初からクルマについていてもおかしくない部品なので、そういう感覚すら生じません。
GVCの開発は、“私たちの考えるクルマとは本来こういうものです”という新しい提案をしたことになるのではと思っています。
日本の自動車分野の産学連携における、理想的なカタチ。
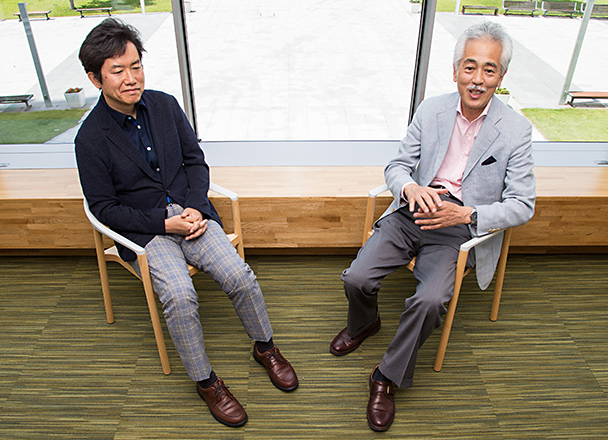
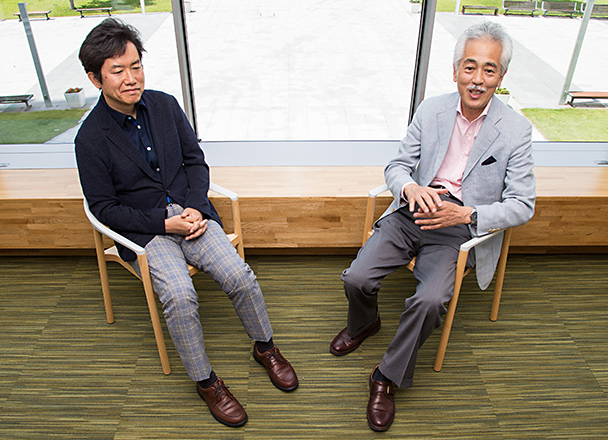
安部教授:
今回の共同開発は、日本の自動車分野の産学連携という観点からも、とても意義深い一例になったと思います。学会には本来、同じ分野の人間が集まり、研究結果などを評価しあうことで、その技術を高めていくという目的があります。
しかし、日本の自動車技術の分野では、競争原理や秘匿主義が働き、どうしてもオープンで活発な意見交換が生まれにくい傾向にあります。
今回のマツダさんと私たちの連携は、一緒に開発を進め、成果を学会に発表し、さまざまな視点によって技術を鍛え続けている。産学連携の理想的な姿を示すことができたのではないでしょうか。
安部教授:
今回の共同開発は、日本の自動車分野の産学連携という観点からも、とても意義深い一例になったと思います。学会には本来、同じ分野の人間が集まり、研究結果などを評価しあうことで、その技術を高めていくという目的があります。
しかし、日本の自動車技術の分野では、競争原理や秘匿主義が働き、どうしてもオープンで活発な意見交換が生まれにくい傾向にあります。
今回のマツダさんと私たちの連携は、一緒に開発を進め、成果を学会に発表し、さまざまな視点によって技術を鍛え続けている。産学連携の理想的な姿を示すことができたのではないでしょうか。
山門教授:
共同開発のパートナーとしてのマツダさんには、まずお互いに意見交換ができる空気がありました。象徴的なのは、「この議論は持ち帰らせてほしい」などと言われた記憶がほとんどないことです。
「この問題を私以上に考えている人はいませんから、この場で決めましょう」と、いつも開発を前に進めてくれました。そして私たちの理論にずっと敬意を払ってくれた。技術名を「G-ベクタリング コントロール」と私たちの理論とほぼ同じ名前にしてくれたことからも、その想いは伝わってきます。
共同開発チームとしてとても望ましい関係を築くことができました。これからもともに、人間中心の車両運動制御技術を探求していきたいですね。